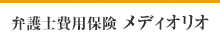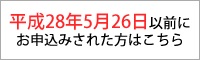お金の大切さ
新NISA
2024年新NISAが始まるので最近、本屋さんにも沢山の関連書籍があり、テレビでもよく見かけ、SNSの広告にもよく現れます。
これからますます投資の気運が高まると思いますが、それに伴い過剰な謳い文句も出てくると思われるのでそれに惑わされないように気を付けたいものです。
個人的には金融商品もかなり多種多様ですので、まずは大まかに分類をしそれぞれの商品特性を調べて少額の金額から始めるのがよいのではないでしょうか? 本屋さんにはそのような書籍も見受けられますので・・・
老後2000万円問題がささやかれ始めたためか、店頭には50代からでも間に合う投資に関する書籍もちらほら見受けられましたので、これから定年を迎えられる方たちには参考になるのではないでしょうか?
それに関連し投資詐欺も増えそうですので気を付けましょう!
医療保険の選び方
ざっくりと作成した資料なのですが医療保険を選ぶ際の参考にしていただければと思います。
保険会社により詳細はこれ以上ありますし、これはあくまでも一つの考え方としてとらえていただきますようお願いします。
*個人的見解にて作成しておりますのであしからずご了承願います。
初めは医療保険です。
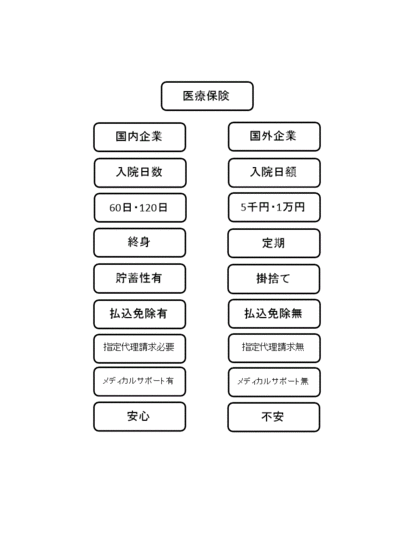
原則、安易に見直さないようにしよう
(3)原則、安易に見直さないようにしましょう。
保険は年齢とともに保険料が上がる商品であるので、目的に合った商品で補償金額もリスクに見合ったものであれば見直さないことが大切です。
本当に必要なものであれば、加入しているベースの保険はそのまま継続して、追加で加入するなど、工夫をしていきましょう。
車の下取りのように保険を下取りにして新品の保険にする方法もあるが、年齢を重ねていてベースの保険の保険料まで上がってしまうので注意が必要です。
目的にあった保険に加入しよう
(2)目的に合った保険に加入できていますか?
「病気リスクに備えたい」という人が死亡保険に加入していたり、「老後リスクに備えたい」という人が掛け捨ての保険に加入していたりと目的にあった保険に加入しているか確認しましょう。
保険選びの3大法則③
(1)若くて健康なうちに保険は検討しよう。
保険商品は、年齢ごとに保険料が高くなる金融商品です。健康診断で何か指摘があったり通院や入院歴があっても定期預金や投資信託は購入できるが、保険商品は条件が付いて保険料が高くなったり加入できないケースもある。年齢が若く健康な間に必要な保険に加入しておけばその後、健康を害しても保証は確保できているので安心。
例えば、医療保険や三大疾病終身保険に加入した場合に,各年齢でどの程度の保険料の差が生まれるのかを考える。もちろん、年齢が上がってからでも全期前納などまとめて保険料を支払えば差は埋められるが、将来の健康状態だけはその時点になってみないと定かではない。保険加入も健康なうちにしっかり検討しておくことが大切。
合計保険料はいくらか?
(3)合計保険料はいくらか?
死亡・病気・障害・老後・介護の5つのリスクの中で、必要な保険と保障金額が明確になったら、各保険会社の保険料と保険商品を調べてみましょう。保険会社と保険商品が決まれば、保険料の払い方も検討。
①払込方法
毎月保険料を支払う月払い、半年後とに支払う半年払い、毎年支払う年払い、さらに一括して支払う前期前納払いなどがある。毎月の保険料は、月払いが割安に感じられますが、合計保険料は、前期前納払いが最も安くなる。前期前納払いは、途中で加入者が死亡するなど、万が一のことがあった場合は、未経過保険料は払い戻されるので、合計保険料を割安にしたい方は検討をされてみてはいかがでしょう。
②払込期間
一生涯支払う終身払い、60歳や65歳まで等、ある一定年齢で払い込みが終了する方法、3年払い、10年払いなど数年で払い込みが終了する方法があります。住宅ローンと同じで長期間支払うことにすれば、一回当たりの保険料は割安にできるが、トータルの保険料は、短く支払った方が安くなる。
③更新型やステップアップ
保険料は払込期間中、一定であるのが一般的であるが一年ごと、あるいは10年ごとなど、途中で保険料がアップする商品もある。年収が年齢とともに上昇していけば、保険料の負担力もアップしていくので、それに対応した方法である。ただし、一定のタイプに比べ、トータルの保険料は高くなるので注意が必要。
加入金額を見積もる
(2)加入金額を見積もる
加入目的が明確になったら、それぞれのリスクに対して、国・企業の保障がいつまでいくらあるのかを確認し、不足する金額を明確にする。
①死亡リスク
死亡した場合、いくら遺族に遺す必要があるか?
国の遺族年金や企業保障などの不足分はいくらくらいになるか?
②病気リスク
日額いくらの入院保障が必要か?
先進医療の費用や自宅療養の費用、休職中の生活費や教育費・住居費などはいくら必要か?
③障害リスク
重い障害になった場合、国の障害年金で不足する金額はいくらか?
④老後リスク
年金が支給されるまでにいくら準備できるか?
貯蓄残高や退職金などを見積もってみる。また、国の年金で不足する金額はいくらか?
⑤介護リスク
あなたが介護状態になった場合に、国の年金や公的介護保険、自分の貯蓄で必要資金をカバーできるか?
不足分があれば、それはいくらか?
あくまでも個人的な考えに基づいてお話をさせていただいておりますので、ご相談はお近くの保険ショップ、ファイナンシャルプランナーへされることをお勧めいたします。
保険選びの3大法則②
加入目的・加入金額・合計保険料を考慮して選ぶ。
(1)加入目的を明確に
子供が小さくて、死亡保障を最優先させたい場合はまず死亡保障をカバーします。独身で死亡した場合の保障は必要ないけれど、病気や障害などの状態になった時の不安がある人は、医療保障を最優先してカバーするなど、保険に加入する目的を明確にすることから始めましょう。また、投資信託などを活用した運用が苦手で、お金が溜まらない人は、掛け捨ての保険ではなく、貯蓄を兼ねた保険も検討するのもよいのではないでしょうか。
死亡・病気・障害・老後・介護の5つのリスクに対して、どんな保証が我が家に、また自分に必要か一つ一つ書き出していくようにされれば、今は何が必要なのかがご理解いただけるのではないでしょうか。
あくまでも個人的な考えに基づいてお話をさせていただいておりますので、ご相談はお近くの保険ショップ、ファイナンシャルプランナーへされることをお勧めいたします。
介護リスクについて
(5)介護リスク
①国の介護保険
会社員や公務員、自営業者を問わず、40歳以上の方は、公的介護保険に加入します。それによって、65歳未満の方は老化が原因とされる病気の場合に、65歳以上の方は、原因にかかわらず、介護状態になった場合に基本的に1割負担で公的介護サービスを受けることができる。
②企業の介護保険
会社員や公務員の方は、介護状態になった場合に、勤務先で加入したグループ保険から介護一時金や介護年金が支給されるケースもあります。それに対して自営業者は何もない。
③個人で加入する介護保険
民間の保険では保険会社独自の介護認定により、公的介護保険で要介護2程度から、介護一時金や介護年金が支給される保険がある。介護状態にならずに死亡した場合は、死亡保険金が一生涯支給される、介護年金付きの終身保険などもある。
上記は概要になっていますので詳細はお近くのファイナンシャルプランナー、全国健康保険協会などでのご相談をお勧めします。
老後リスクについて
(4)老後リスクについて
①国の老齢年金
会社員や公務員の方は65歳などになると、老齢厚生年金(退職共済年金)+老齢基礎年金が一生涯支給される。それに対して自営業の方は、基本老齢基礎年金のみ。
②企業の退職金
会社員や公務員の方は定年後退職金や企業年金が支給されます。それに対して自営業の方は自分で小規模企業共済や国民年金基金・確定拠出年金などを積み立てていない限り、何も支給されません。
③個人で積み立てる年金
①や②で不足する金額や不足する期間分は、民間の保険会社などで個人年金を積み立てたり、銀行や証券会社で預金や投資信託などで積み立てることが大切。特に①、②が少ない自営業の方は、定年がないとはいえ、不足分が会社員に比べて多いため、意識して準備しておくことが大切です。
上記は概要になっていますので詳細はお近くのファイナンシャルプランナー、日本年金機構事務所などでのご相談をお勧めします。

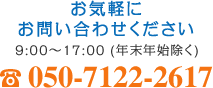
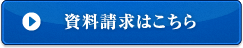
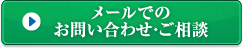
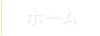
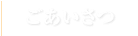

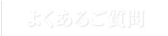
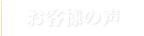
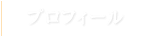
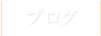
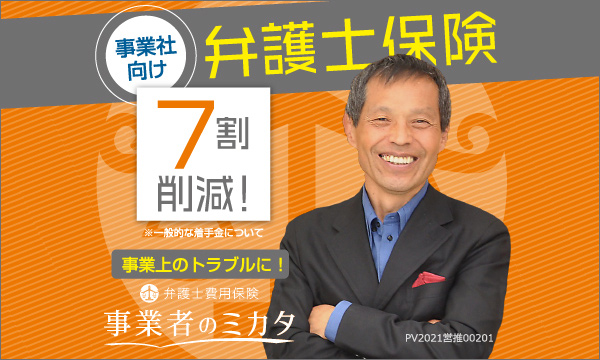


(1).png)